|
|
The Ceramic Society of Japan |
|---|---|
| | CerSJ トップページ | 部会・支部 | 東海支部トップ | | | Japanese | English | |
[東海若手セラミスト懇話会]
[日本セラミックス協会東海支部]
日時:平成 18 年 10 月 26 日 〜 28 日
場所:大垣フォーラムホテル(岐阜県大垣市万石町 2-31)
この会はセラミックス分野で研究開発を行っている若手研究者・技術者が,それぞれの成果を口頭およびポスター形式で発表し有用な情報を交換することのみならず,会を通じて互いの人物を知り合うことで国際的な人的ネットワークを築き上げ,国際的な共同研究が推進されることを目的として企画されました.また日本のセラミックス分野で中心的な地区である東海地方で活動している若手セラミストが良い刺激を受け,今後の研究開発に大いに役立つことを期待し,開催されました.
今回初の試みとなりましたが,一般参加者:54 名(内 企業:19 名,国公研:10 名,大学教員:12 名,学生:13 名)招待講演講師:9 名と合計 63 名といった多くの方々にご参加頂きました.さらにゲスト参加者として 5 名ご参加頂きました.また会期中,招待講演 10 件,ポスタープレゼンテーション 62 件(招待者も含む参加者全員)の発表が行われました.以下,進行順に内容を報告いたします.
1日目
18:30 から,御挨拶として東海支部長・淡路英夫先生(名工大)より上記に示しました本会議の趣旨,期待することなど説明があり(写真 1),本会議が開催されるとともにウェルカムパーティーが始まりました.その後,実行委員長・津越(産総研)による司会の下,招待講演者の紹介(写真 2)などが行われ,終始,出席した研究者間での交流が図られました(写真 3)
2日目
9:00 より招待講演者によるプレゼンテーション及びポスター発表の 1 分間スピーチが行われました.なおポスター発表の数から 1 分間スピーチは 3 つに分けられました.この1分間スピーチはポスター発表内容をアピールすることを目的としています.さらにレクリエーションによって人的交流を行い、夕方より交流会を兼ねたポスター発表が行われました.以下 2 日目の概略を報告します.
Jing-Feng Li 氏 (Tsinghua University)
“Piezoelectric Ceramic Films and Micro-structures for MEMS Applications”
プリンターやアクチュエータなどに用いられる PZT薄膜の合成とその特性向上について研究報告がなされました.基板に PbO や TiO2 などの seed となる薄膜を製膜した後, PZT を製膜することで結晶配向制御し,圧電特性の高い薄膜作成が可能となったこと,これがデバイス等への応用が期待されることなどを説明されました(写真 4).
Hae Jin Hwang 氏 (Inha University)
“Sol-gel Technique for Energy-related Materials Synthesis”
高気孔率や低密度などから高い断熱性,低い誘電特性などをもち,多分野でその応用が期待されているシリカエアロゲルの合成について,今回水ガラスをベースとした大気中で行うより安価な合成を報告されました.特により大きなエアロゲル成形について再現性にもふれ,実用化に趣をおいた研究内容について発表されました(写真 5).
→ここで,1 回目のポスター発表の 1 分間スピーチがなされました.
Hong Lin 氏 (Tsinghua University)
“Quasi-solid Dye-sensitized Solar Cells with Composite Electrolyte”
近年注目される太陽電池の中でもシリコンを用いず,フィルム状に加工可能なことからセラミックやプラスチックに接着できる色素増感太陽電池について最近の研究開発動向を交えながら現在の研究内容について発表して頂きました.今回は太陽電池の効率を上げるための研究として,リン酸ジルコニウム添加による色素増感太陽電池のエネルギー変換効率への影響について報告されました(写真 6).
Ji-Woong Moon 氏 (Korea Institute of Ceramic Engineering and Technology)
“Synthesis of Clay-based Nanocomposite by Intercalation”
モンモリロナイトやスメクタイト,アロフェンなどの層状粘土鉱物に無機/有機化合物を添加し,層間に架橋することで新たな特性を付与することが研究されており,今回モンモリロナイトに両性イオンであるアミノ酸をインターカレートする研究を説明して頂きました.アルギニン,ヒスチジン,リジンといった塩基性アミノ酸がインターカレーションに有効であるとのことでした(写真 7).
Tanguy Rouxel 氏 (Universite de Rennes)
“Designing Glasses to Meet Specific Mechanical Properties”
ガラスはもろい材料であるものの,その種類は多種多様であり,物性も大きく変化するため,構造や構成される元素など組成制御して,ヤング率やポアソン比など目的とする物性を有するガラス材料を開発する研究について報告して頂きました(写真 8).
Guo-Jun Zhang 氏 (Shanghai Institute of Ceramics)
“Zirconium Diboride-Based Ultra-high Temperature Ceramics(UHTCs)”
宇宙などの極限環境では,高温材料として知られる SiC や,TiC,Si3N4 などでは使用困難であるため,さらに高温特性が優れるホウ化物が着目されています.そこでホウ化物の低温焼結に関して発表して頂きました.今回は,SiC を用いて比較的低温(約 1800℃)で反応焼結させてホウ化ジルコニウム系の超高温材料の開発について報告して頂きました(写真 9).
→ここでポスター発表の 1 分間スピーチ 2 回目が行われました.
Tarek Agag 氏 (Tanta University)
“Synthesis and Properties of Some Novel Polymer Nanocomposites Using Organoclays”
ナノサイズの層状化合物(モンモリロナイト)を樹脂に添加して有機−粘土複合体を調製する技術について報告して頂きました.樹脂中にフィラーとして層状化合物を均一分散させることで通常の樹脂と比較してガラス転移点など粘弾性特性が大きく向上した成果についてわかりやすく説明して頂きました(写真 10).
講演終了後,会場に隣接するボーリング場にてボーリング大会を行い,交流を図りました.研究の内容以外にもレクリエーションで汗を流すことで会話のきっかけや親近感などがありそれぞれのチームやこれを超えた交流ができました(写真 11).
懇親会を兼ねたポスター発表では,はじめに本会の実行委員長である津越より挨拶があった後,セラミックスの若手研究員の交流がなされました.ここでは先のレクリエーションの効果もあり,初日よりもいっそううち解けた雰囲気で料理を楽しみながら会話に,議論に花を咲かせ交流を深めました.しばらくの歓談の後,ポスター発表が行われました.ここではコアタイム 40 分間で 3 つのグループに分けられ,活発なディスカッションが各ポスターの前で行われました.また招待講演者にもポスターを掲示して頂き,講演内容について発表の場で聞けなかったことなど活発に議論されました(写真 12 〜 14).
また終了間近にボーリング大会のチーム及び個人それぞれ 1 位, 2 位を表彰しました(写真 15).個人については,今後の成長の可能性が最も大きいという意味を込めてブービー賞も表彰致しました.
最後に東海若手セラミスト懇話会の創設者でもあります伊藤先生(名大)よりご挨拶頂きました(写真 16). 東海地区に限らずアジア地域のセラミックスの若手研究者が交流の場を持ち,国際交流を深め,国境をこえた共同研究,成果に結びつく芽を育成していくことは重要であり,初めての試みとして行った本会議について,できれば今後何年単位にでも実現してほしいとの言葉を頂きました.このポスター発表及び交流会の時間はあっという間に過ぎていき,全員で記念写真を撮影した(写真 17)後も議論がなされる場面が多々ありました.その後,場所を 2 次会場に移した方も多数おり,夜更けまで議論は続き,親睦を深めたようです.
3日目
Takashi Ida 氏 (Nagoya Institute of Technology)
“Evaluation of Crystallite size by Powder X-ray Diffraction Method”
比較的安価であり,未知試料の鉱物同定や結晶構造の定性定量その他いろいろな用途に用いられる X 線回折 (XRD) ですが,結晶子サイズを評価する場合, X 線の線源や検出器の精度などの影響を考慮して解析することが重要です.そこでこれらの影響を加味した解析方法についてこれまで検討した結果を報告して頂きました(写真 18).
Yanfeng Gao 氏 (Musashi Institute of Technology)
“Controlled Crystallzation of TiO2 and ZnO from Aqueous Solutions: Effects of Soluble Organics”
光触媒や次世代の透明電極などに期待される TiO2 や ZnO について,水溶液からの薄膜形成制御について報告されました.特に ZnO 及び TiO2 薄膜の生成過程について,これまで得られた知見を元に研究報告して頂きました(写真 19).
Balagopal N. Nair 氏 (Noritake Co. Ltd.)
“Development of Ceramic Materials and Structures for Emerging Applications in Hydrogen Economy”
次世代の発電システムとして期待される燃料電池においてセラミックスの新たな市場開拓として,水素の精製やガスフィルター,触媒,固体電解質など燃料電池の部材としてもちいるセラミックス材料の開発についてこれまで行ってきた研究内容をわかりやすく説明して頂きました.(写真 20)
Takahisa Tsugoshi 氏 (National Institute of Advanced Industrial
Science and Technology)
“Collaboration between The Next Generations”
本会の経緯,趣旨について参考にした,やはり津越氏がオーガナイザーを務める日本分析化学会のアジア若手分析化学者交流会を例に挙げながら説明頂きました.また自分の経験や若手(40 歳以下)を対象とした補助金制度などにもふれ,国際的に共同研究を行い,成果を出していくことは重要なことであると説明頂きました(→写真 21).
最後に海外よりの招待講演者に感謝の意とともに,東海地区研究者との交流継続の積極性への期待を込めて表彰状と記念品が贈られました(→写真 22, 23)(写真 24: 記念品の裏印). そして津越実行委員長により閉会の挨拶があり閉会いたしました.その中で,本会での人脈ネットワークを継続するために AYCeCT のウエブページを是非活用頂きたいこと,またアジア地区全体で本会を盛り立てる AYCeC (Asia Young Ceramist Conference) の提案がなされ,特に海外招待者には大きな関心を集めました. 今回の会議は初の試みでしたが,通常の国際会議とは違った終始和んだ雰囲気の中でアジア地域を中心とした若手セラミストが親睦を深める良い機会となりました. 本会をきっかけとする国際共同研究が発足し,相互国間のより親密かつ有益な関係が構築されることを実行委員一同願っております.
また学生参加費を設定しなかった本会に,学生の参加者が 13 名を数えたことは,今後の若手の活動にとって特筆すべき事項であり,大変にたのもしい限りと考えます.
 写真1 |
 写真2 |
 写真3 |
 写真4 |
 写真5 |
 写真6 |
 写真7 |
 写真8 |
 写真9 |
 写真10 |
 写真11 |
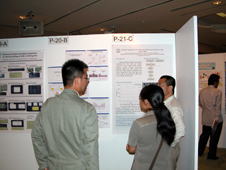 写真12 |
 写真13 |
 写真14 |
 写真15 |
 写真16 |
 写真17 |
 写真18 |
 写真19 |
 写真20 |
 写真21 |
 写真22 |
 写真23 |
 写真24 |
[開催案内を見る]
[若セラ2006夏期セミナー報告] ←
→ [若セラ2007夏期セミナー報告]
[平成18年度事業]
2006年10月28日 掲載
2014年11月19日 更新