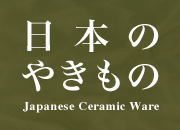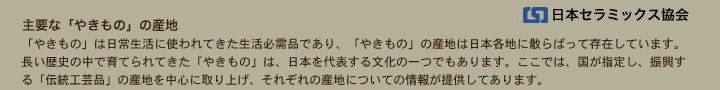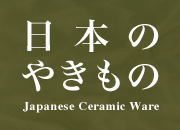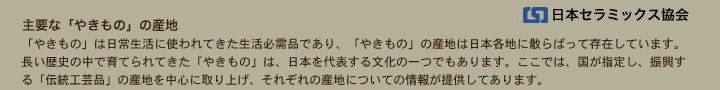室町時代末期から、尾張や美濃地方はやきものの町として栄えていました。しかし、絶えず合戦の舞台にもなっていました。そこで、彼の地の陶工達は全国に焼き物ができる土地を求めて旅立ちました。東北地方を、目指した者の中に、瀬戸出身の水野源左衛門、長兵衛の兄弟がいました。彼らは、やがて長沼(福島)で故郷の粘土に大変よく似た原料を見つけ出し、ここに留まって焼き物を作り始めました。 室町時代末期から、尾張や美濃地方はやきものの町として栄えていました。しかし、絶えず合戦の舞台にもなっていました。そこで、彼の地の陶工達は全国に焼き物ができる土地を求めて旅立ちました。東北地方を、目指した者の中に、瀬戸出身の水野源左衛門、長兵衛の兄弟がいました。彼らは、やがて長沼(福島)で故郷の粘土に大変よく似た原料を見つけ出し、ここに留まって焼き物を作り始めました。
その頃、会津藩主保科正之公は領地内で製陶をはじめた兄源左衛門を呼んで、会津に焼き物を誕生させるように命じました。源左衛門は原料探しのために会津の山々を調査し、遂に本郷の地に良質の粘土を発見しました。そして、苦心の末に「凍み割れしない瓦」を完成させたのです。保科公はその功績を称えて、弟長兵衛に瀬戸右衛門という称号を与えました。
それ以後、会津本郷焼は脈々とその技を受け継ぎ、現在に至ります。
|