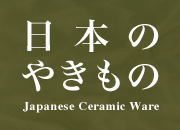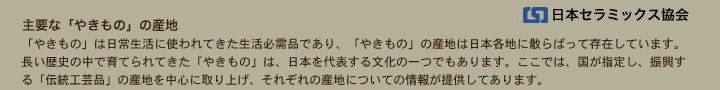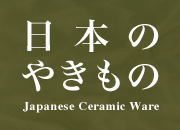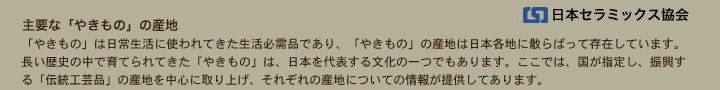|
 古伊賀と呼ばれるやきものは、桃山時代に筒井定次が伊賀領主となってから作られるようになったとされます。その後、「織部好み」と呼ばれる芸術的な色彩を帯びた茶陶が作られるようになりました。藤堂家三代目の高久の時代に伊賀陶土の乱掘を防ぐ制度が設けられた際に、多くの陶工が信楽に移り、一時衰退しました。18世紀に入り藤堂家九代目の高嶷が作陶を奨励、これにより「再興伊賀」の時代を迎えました。明治期以降、伊賀陶土の特性を生かした耐熱食器の生産が主流となり、産地としての基盤が固められました。 古伊賀と呼ばれるやきものは、桃山時代に筒井定次が伊賀領主となってから作られるようになったとされます。その後、「織部好み」と呼ばれる芸術的な色彩を帯びた茶陶が作られるようになりました。藤堂家三代目の高久の時代に伊賀陶土の乱掘を防ぐ制度が設けられた際に、多くの陶工が信楽に移り、一時衰退しました。18世紀に入り藤堂家九代目の高嶷が作陶を奨励、これにより「再興伊賀」の時代を迎えました。明治期以降、伊賀陶土の特性を生かした耐熱食器の生産が主流となり、産地としての基盤が固められました。 |
|
|
|
|
 窯変によるビードロというガラス質や焦げ、器そのものの力強い形や色が伊賀焼の特徴とされます。古伊賀と呼ばれる茶陶は、せつ器質胎の白色粘土を用い、織部好みと呼ばれる歪みの激しい造形、自然釉や焦げの景色を尊ぶ豪快な侘びを持つ作風です。一方、再興伊賀は施釉陶の日常雑器が中心となり、雪平鍋、土瓶、土鍋などが庶民に支持を受けて全国に広まりました。 窯変によるビードロというガラス質や焦げ、器そのものの力強い形や色が伊賀焼の特徴とされます。古伊賀と呼ばれる茶陶は、せつ器質胎の白色粘土を用い、織部好みと呼ばれる歪みの激しい造形、自然釉や焦げの景色を尊ぶ豪快な侘びを持つ作風です。一方、再興伊賀は施釉陶の日常雑器が中心となり、雪平鍋、土瓶、土鍋などが庶民に支持を受けて全国に広まりました。 |
|
|
|
|
 伊賀焼に使用する陶土は「青岳蛙目粘土」、「島ヶ原蛙目粘土」、および「丸柱粘土」、または、これらと同等の材質を有するものとすることが定められています。これらは高温まで耐えられる陶土ですので、作品は火に強く丈夫なものになります。 伊賀焼に使用する陶土は「青岳蛙目粘土」、「島ヶ原蛙目粘土」、および「丸柱粘土」、または、これらと同等の材質を有するものとすることが定められています。これらは高温まで耐えられる陶土ですので、作品は火に強く丈夫なものになります。 |
|
 |
| 伊賀焼伝統産業会館 |
|
| (参考・写真転載:伊賀焼パンフレット「伊賀窯変」、「伊賀焼伝統工芸士」より) |
| |
|
| |