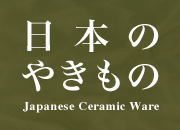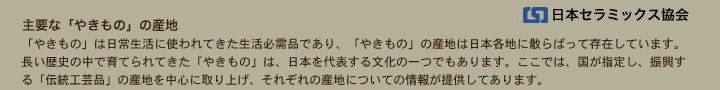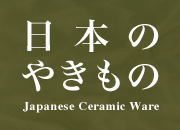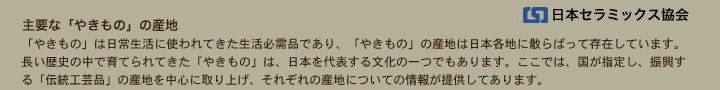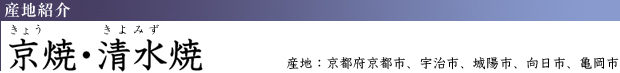 |
 室町時代に中国の明から伝えられた交趾釉法の内焼が行われ、色絵陶器が始まりました。一般には桃山時代から京都で始められた近世を代表する陶磁器を京焼と呼びます。その後、野々村清右衛門が錦手の秘法を会得し、京焼・清水焼のひとつの大きな頂点を迎えました。 室町時代に中国の明から伝えられた交趾釉法の内焼が行われ、色絵陶器が始まりました。一般には桃山時代から京都で始められた近世を代表する陶磁器を京焼と呼びます。その後、野々村清右衛門が錦手の秘法を会得し、京焼・清水焼のひとつの大きな頂点を迎えました。 |
|
|
|
|
 京焼・清水焼は、京の都で親しまれた茶の湯の文化から生まれたとも言われます。都独特の華やかさと洗練された美しさを持ち、いつの時代にも多くの名工が輩出し、現代へと系譜を繋いでいます。現在では、山科や炭山地区に陶工たちが集団移転し、新しい創造に意欲を燃やしています。 京焼・清水焼は、京の都で親しまれた茶の湯の文化から生まれたとも言われます。都独特の華やかさと洗練された美しさを持ち、いつの時代にも多くの名工が輩出し、現代へと系譜を繋いでいます。現在では、山科や炭山地区に陶工たちが集団移転し、新しい創造に意欲を燃やしています。 |
|
|
|
|
 現在は陶土を産しないので、天草陶石・柿谷陶石・信楽粘土・伊賀粘土などを移入して製作しています。焼成は、京式登窯から、公害防止のために電気窯やガス窯に移行しており、これらの変化で工程が合理化され、生産性が向上しています。 現在は陶土を産しないので、天草陶石・柿谷陶石・信楽粘土・伊賀粘土などを移入して製作しています。焼成は、京式登窯から、公害防止のために電気窯やガス窯に移行しており、これらの変化で工程が合理化され、生産性が向上しています。 |
|
 |
|
| 京都の風景 |
|
|
| |
| (参考・写真転載:京焼・清水焼通信、京都伝統工芸協議会パンフレット「京焼・清水焼」より) |
| |
|
| |