 |
 備前はわが国六古窯の一つと言われます。延喜式には須恵器の産地として名が挙げられ、鎌倉末期から南北朝時代にかけて備前焼の特徴を備えたやきものが現れます。この頃より窯数も増加して生産量が増し、西日本各地に流通圏が拡がります。十六世紀後半には、無釉焼締のやきものが侘茶の道具として好まれるようになり、伝統は現代に続いています。 備前はわが国六古窯の一つと言われます。延喜式には須恵器の産地として名が挙げられ、鎌倉末期から南北朝時代にかけて備前焼の特徴を備えたやきものが現れます。この頃より窯数も増加して生産量が増し、西日本各地に流通圏が拡がります。十六世紀後半には、無釉焼締のやきものが侘茶の道具として好まれるようになり、伝統は現代に続いています。
|
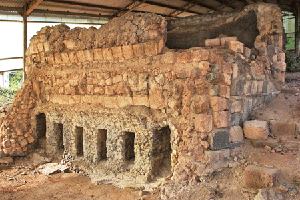 |
| 古窯 |
|
|
 備前焼は、田土を用いた無釉で焼締陶器の伝統を守り、日常生活品である大水甕や壷、擂鉢などを生産してきました。それと共に無釉の特徴を生かした、水指や花生、花瓶、徳利、茶壺などの茶陶を生産してきました。現在でも、胡麻(ごま)、桟切り(さんぎり)、火襷(ひだすき)等の焼締の特徴を生かしたやきものの生産を続けています。
備前焼は、田土を用いた無釉で焼締陶器の伝統を守り、日常生活品である大水甕や壷、擂鉢などを生産してきました。それと共に無釉の特徴を生かした、水指や花生、花瓶、徳利、茶壺などの茶陶を生産してきました。現在でも、胡麻(ごま)、桟切り(さんぎり)、火襷(ひだすき)等の焼締の特徴を生かしたやきものの生産を続けています。 |
| |
|
|
|
| |
 備前焼伝統産業会館では、2階展示場において備前焼陶友会会員の作品を
展示販売し、ギャラリーにおいては、リレー個展を通年開催している。
備前焼伝統産業会館では、2階展示場において備前焼陶友会会員の作品を
展示販売し、ギャラリーにおいては、リレー個展を通年開催している。
また、岡山県備前陶芸美術館では、古備前から現代作家の作品を一堂に集め展示している。
|
 |
| 備前焼の里 |
|
| |
|
| |