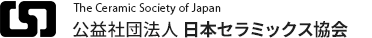会長挨拶(会長就任のご挨拶)

会長 細野 秀雄
会長就任のご挨拶
この度6月5日開催の日本セラミックス協会定時総会において、村田恒夫会長の後任として選任されました細野秀雄と申します。宜しくお願いします。
私は大学院生の時からほぼ20年間は酸化物ガラスと結晶化ガラスを研究対象とし、本協会を主な活動の場としてきました。それ以降は無機系固体物質を対象とすることは不変ですが、テーマを電子が主役を演じる機能の創出を目的として、酸化物半導体、超伝導、エレクトライド、そして触媒などに広げてきました。それに応じて発表の場は、半導体関係は応用物理学会とMRS、超伝導は物理学会とAPS、エレクトライドは日本セラミックス協会とACS というように、テーマに最も即した学会を選んできました。その関係で内外の関連学会の特徴と価値観の違いを多少は理解できたと思っています。本会の一つの特徴は、長い歴史を有するセラミックス(無機材料)に関する国内最大の学術団体で、約200 社に及ぶ多くの企業会員を有することでしょう。分野横断型の学会は、いろいろな領域に属する会員が参集しますので、学際的な取り組みが加速できることが大きなメリットですが、企業会員が少なく資金面や産学の交流の機会で苦労しています。
数多ある物質の中で、人間社会に直接役立つものが材料です。「使われてこそ材料」といわれるゆえんです。物質から材料にジャンプできるものは稀で、物質の特性だけでなく、社会のニーズとマッチングが必要です。大きな産業応用に繋がった材料の創出には、当初は意図しなかったユニークな特性の発見とそれを支える学術研究が不可欠のようです。本会が対象としている材料は、無機固体物質です。この物質系では、周期表のほぼすべての元素を構成要素とすることができます。しかも多くの場合、多結晶体なのでバルクとは構造と物性が不連続な粒界が多数存在します。よって、理論的な扱いが難しく、進展が遅れがちです。しかし、近年のAl の進展でコンピューターが目を有することになり、結晶粒界の分布や構造などが情報として捉えられるようなり、物性と関係づけられる手法が登場してきました。また、第一原理分子動力学計算も、DFT 計算によるデータを学習させることで決めたポテンシャルを使うことで、原子数や時間発展の制約がかなり緩和され、現実の物質系を扱えるようになりつつあります。これらは、セラミックスの研究を大いに加速できる手法だと思いますので、貪欲に取り入れて欲しいものです。物性物理の領域でも、これまで単結晶を前提とした研究から粒界を含めた不均一系へ対象を広げようという試みも始まっています。固体物質を正面から扱うには化学と物理の両方が不可欠ですので、固体物理の分野とも交流ができれば双方にとって有益ではないでしょうか。
大きな可能性を秘めたセラミックスですが、少々気になることがあります。それはJST やNEDO などの研究プロジェクトに、セラミックスらしいテーマで採択されるケースが少ないことです。インパクトのある研究成果が大前提ですが、隣接分野の研究者にも重要性の理解を促す更なる努力が必要だと感じています。CO2 削減や資源問題への対処は産学が連携して強力に進める必要のある課題です。そのためにも大型の国プロの立ち上げが有効と思います。
無機固体物質に秘められた可能性は膨大です。この20年以内に限っても、鉄、ニッケル基高温超伝導体、HfO2 系などの非ペロブスカイト強誘電体、ヨウ素系ペロブスカイト太陽電池など予期できなかった大きな発見がそれを如実に表しています。日本の学会の中で、無機固体物質の科学と技術、および合成プロセスを専門的に扱う最大規模の学会として、本会の果たせるポテンシャルも大きいと感じています。
Hideo HOSONO(President, The Ceramic Society of Japan)
An Inaugural Address