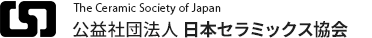会長挨拶(新年のご挨拶)

会長 細野 秀雄
新年のご挨拶
新年 明けましておめでとうございます。
昨年は、2 件のノーベル賞受賞、そして日本人 3 選手の大活躍によるドジャースの優勝など明るいニュースがありました。前者はシニアの研究者による 30 年ほど前からの開拓的な研究の成果が評価されたもので、後者は若手が海外へ飛躍して成したものです。このような日本人の活躍は、我々に元気を与えてくれます。一方、社会にも大きな変化がありました。生成 AI の本格的な社会実装が急速に進みつつあることです。現在までに蓄積された膨大なデータを極めて迅速に処理して整理することが可能になりました。過去のデータに依存しているので、その限界は理解しているつもりでも、その処理速度には舌を巻いてしまいます。あるジャーナルから総説の執筆依頼を受けた際に、執筆要項に生成 AI でまとめたものを独自の視点なしで原稿としないことと書かれているのには驚きました。筆者が大学から大学院生のころ(1980 年前後)、電卓が普及し計算尺や対数表が姿を消し、ワープロが普及しタイプライターが不要になりました。生成 AI は「電脳」ともいえる道具の出現で、電卓やワープロのそれとは質的に違う変化だと思います。我々の生活や仕事にも多大の影響をもたらすことは間違いないでしょう。
恒例に従い、本協会の今年度に予定されていることを以下に記します。3 月に横浜国大で開催の年会では、セラミックスアート、AI を駆使した多結晶材料情報学、先端固体物性などの新企画をサテライトとして開催予定です。アートは材料のなかでセラミックスと際立って相性がいいので、新しい科学の目で見直すいい時期かと思います。AI や固体物理はセラミックスの研究のジャンプアップに是非とも必要なものなので、積極的に取り入れていく先鞭になることを期待しています。9 月には ICC11 が札幌で開催されます。これは秋季シンポジウムとの併催となります。この会議の Plenary speaker には今年から始まる国際フェローの受賞者も含まれることになっています。また、新しく始まったセラミックス遺産認定制度の第一回選定も今年発表されます。年度にまたがるものとしては中期経営計画(2026 ~2028 年度)の開始年度にあたります。セラミックス協会の魅力度向上と財政基盤強化を大方針とした計画を策定中です。少子化にともなう労働人口の減少で、国内のほとんどの学協会では会員数が過去10 年間でかなり減少しており、財政的に苦戦を強いられております。本協会は、企業会員が多く、正・学生会員数の減少にも歯止めがかかっておりますので、危機的状況には至っておりませんが、協会の建物の老朽化に伴い対応が必要になっております。年会の国際化などを実施して海外からの会員を増やすことも真剣に検討する時期かもしれません。
最後に個人的な意見を記させて頂きます。昨今の内外の研究のトレンドを眺めると、“セラミックス~窯業”という感覚では、対象物質に秘められた大きなポテンシャルを十分に生かすことは困難だと感じています。窯業の伝統を踏まえて、無機固体材料の科学と工学を専門に扱う国内最大の学協会として、発展を図るのがこれからの方向でしょう。そのためには、対象物質に適した新しい研究手法の貪欲な導入と新しい応用の可能性を大胆に探ることは、本協会のこれからの大きなミッションになると考えます。いかがでしょうか。
Hideo HOSONO(President, The Ceramic Society of Japan)
Presidential New Year's Address