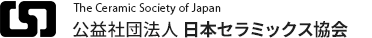ダイバーシティ四季感 ー会員間をリレー形式でつなぐ雑記帳ー
| セラミックス誌 2026年1月号掲載 (No.37) |
私立大学の教育・研究の現場に身を置くと,日々,学生の成長を通して多様性の価値を実感いたします.研究室には,几帳面にデータを積み重ねる学生もいれば,失敗を恐れず新しい条件に挑む学生もいます.議論では,理論を丁寧に展開する学生もいれば,直感的な着想を次々に示す学生もいます.最初は互いの違いに戸惑い,衝突を経験しますが,やがて視野を広げ,柔軟に考える力を養います.こうした個性の交わりが,学生を大きく成長させるのです. (千葉工業大学 橋本 和明) |
| セラミックス誌 2025年10月号掲載 (No.36) |
私は歯科補綴専門医として,歯の欠損を有する患者の審美性や機能回復を目的に,補綴装置を用いた診療を行っています.臨床現場で常に意識しているのは,「Science & Art」という概念と,それを支えるダイバーシティです. (東京科学大学 野崎 浩佑) |
| セラミックス誌 2025年7月号掲載 (No.35) |
私の所属する研究室の学生の男女比は1:1,学生のバックグラウンドは化学・材料・物性物理・臨床検査・歯学・医学,留学生比率は28%です.もし,研究室のダイバーシティを点数化することができれば,相当に優秀な点数になると思います.今の研究室の姿は多様性を求めた結果ではなく,自然に今の姿になりました.昨今は多様なコミュニティを作らなくては“ならない”,という言わば多様性圧力とでもいうような目に見えないモノがあるような気がしますが,それとは無関係に多様性に溢れた研究室が出来上がってきているという点を私はとても気に入っていて,そんなに無理をしなくても,条件さえうまく整えれば多様性は自然なカタチで生まれるのではないかなと私は思っています.私の所属していた東京医科歯科大学は昨年の10月に東京工業大学と合併し,東京科学大学になりました.これを機に,自然にさらにダイバーシティに富んだ楽しく活気に満ちた研究室になっていくことを期待しています. (東京科学大学 横井 太史) |
| セラミックス誌 2025年4月号掲載 (No.34) |
通勤途中,登校中の小学生の集団をよく見かけます.背中にあるのは色とりどりのランドセル.筆者が小学生のときは,ほとんど黒か赤で,しかも,女子は赤,男子は黒,という陣容でした.最近ではそもそも様々な色のランドセルが販売されており,性別に関係なく色を選択できるようになっています.そして小学生はそれを当たり前のことと受け止めて自分の好きな色を選んでいるように思います. (名古屋大学 小林 亮) |
| セラミックス誌 2025年1月号掲載 (No.33) |
ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)でよく言及されるのは性別,人種,年齢,性的指向,障がいの有無,宗教,価値観などですが,ここでは研究の観点からD&Iについて考えてみたいと思います. (香川大学 原 光生) |
| セラミックス誌 2024年10月号掲載 (No.32) |
ダイバーシティ「多様性」というと,性別や人種,国籍の多様性が最初に挙げられます.一方で研究者の多様性としては,異なるバックグラウンドや経験も,研究組織に新たなアイデアや豊かさをもたらす重要な要素と考えています. (大阪大学 神戸 徹也) |
| セラミックス誌 2024年7月号掲載 (No.31) |
日本では,「ダイバーシティ=性差」という観点での話が多いが,性差以外にも国籍,人種,宗教などの多様性があり,残念なことに世界中でこれらを発端とした衝突が起きている. (千葉大学 塚田 学) |
| セラミックス誌 2024年4月号掲載 (No.30) |
ダイバーシティ&インクルージョンの推進における問題は,「マジョリティ側が自らの特権に無自覚であること,および,社会の構造的な不平等について理解が及ばないこと」だそうだ.日本生まれの日本人・男性である私は,職場コミュニティにおいてマジョリティ側にいると言える.マジョリティ側は,労せずして特権を得ているのであるがそれを自覚していないそうである.これはどういうことか?自分自身について考えてみた. (大阪公立大学 徳留 靖明) |
| セラミックス誌 2024年1月号掲載 (No.29) |
人と物の往来や情報通信網の発達などにより,「ダイバーシティ」を大切にする社会が形成されようとしていることは喜ばしいことです.日本は特に,つい180年前まで鎖国をしていた国であり,現代においても外国人をどのように受け入れるかという問題は根深いと感じています.私の所属する研究室にも多くの外国人ポスドクや学生がいますが,言葉や文化の壁を乗り越えてともに働きともに成長するにはどうすれば良いのでしょうか? (京都大学 金森 主祥) |
| セラミックス誌 2023年10月号掲載 (No.28) |
経済産業省が策定した「Diversity 2.0」は,「多様な属性の違いを活かし,個々の人材の能力を最大限引き出すことにより,付加価値を生み出し続ける企業を目指し,全社的かつ継続的に進めて行く経営上の取組」と定義されている.その取り組みのひとつに,「女性活躍の推進とともに,国籍・年齢・キャリア等,様々な多様性の確保」が挙げられている.現在,本部組織の国際室で海外連携を担当していることもあり,ここでは,グローバル化について言及したい. (産業技術総合研究所 髙田 瑶子) |
| セラミックス誌 2023年7月号掲載 (No.27) |
昨今の「ダイバーシティ」といえば「女性」と解釈されること当たり前になっていると感じられる.ダイバーシティとは多様性を意味するもので,性別はその一つに過ぎないと考えている.一方,男女という性別は,ダイバーシティの中で最も一般的で分かりやすいもので,ダイバーシティを推進する足掛かりとして注目されたかもしれない.性別以外の多様性として,国籍,年齢層,文化圏,学歴,職業などもあるので,これから注目されることを願う. (産業技術総合研究所 李 誠鎬) |
| セラミックス誌 2023年4月号掲載 (No.26) |
コロナ禍では職場において実に様々な変化が起きました.私個人においてその最大は,オンラインを活用したコミュニケーションです.職場の小さい単位の会議,大きな国際会議,そして大学講義など,多くの活動がオンラインで実施可能であることを認識するとともに,その利点と欠点を学ぶことができました.これらの経験はダイバーシティの推進に活用できると考えます.例えば勤務地や勤務形態の柔軟化です.育児や介護との両立を可能としたり,勤務場所・時間の自由度を高めたりすると考えます.大学のような教育機関であれば,国際的人材の育成にも有用です.上記のようなことは多くの人が思いつく内容ですが,果たしてどれほどが実行に移されているのでしょうか.コロナ禍の明けた先に「元の生活」を求めるのではなく,「新しい生活」をつくるべきとも言われます.その中にはさらに発展したダイバーシティ環境も含まれるのでしょう.私個人ができることは些細な事ですが,できることから始めない限り何も変わりません.まずは身近な半径数m範囲から取り組みたいと考えています. (名古屋工業大学 小幡 亜希子) |
| セラミックス誌 2023年1月号掲載 (No.25) |
ダイバーシティとは何か,改めて調べてみると実に”多様な”解釈があるようです.私は現在,学部6名,修士7名の合わせて13名と一緒に研究しており,うち5名が女性でみな大学院に進学します.配属・進学に際して,研究室に女性の先輩もいて安心感もあった,といった声も聞きました.進路は自分の意思だ,とは当然だがやはり周りの環境も影響すると思います.女性の教員や研究者を増やしたい,という国内の流れも,研究活動に興味ある女性学生さんにとってもよりよい環境となることは間違いないでしょう. (名古屋工業大学 大幸 裕介) |
| セラミックス誌 2022年10月号掲載 (No.24) |
言葉には力がある.言霊という言葉はその力をよく示している.若かりしころ“24時間働けますか“と連日CMが流れ,働くことを刷り込まれたように(当時でも労働基準法違反である),言葉の力を利用することは古今東西行われてきた(昨今は”SDGs“ ?). (日本大学 井口 史匡) |
| セラミックス誌 2022年7月号掲載 (No.23) |
私がこのコラムの執筆を依頼された同じ頃,偶然,妻も所属学会からダイバーシティに関わる講演依頼をされ,二人でどういう内容が良いかねと話しました.自分の経験を振り返ってみると,15年前のスイス留学時の事が思い浮かびました.ラボでは常勤研究者は女性の方が多く,一人は私の滞在中に出産・復職と公私ともフル回転でした.学生も多国籍かつ多種多様でエネルギッシュでした.国民性は日本以上に保守的な部分も多いスイスでしたが,小国であるがゆえ産業や研究という分野ではオープンである事が競争力や成長に直結するという合理的判断があるのだと思います.翻って日本では今でもダイバーシティを渋々やらねばという空気がある気がしますが,むしろ人口減の時代に,これまで使い切れていない潜在的な成長領域を我々がどう使いこなすかが問われていると感じています. (東北大学 八代 圭司) |
| セラミックス誌 2022年4月号掲載 (No.22) |
ダイバーシティ四季感のリレーコラムの原稿を依頼され,真っ先に思い出したのは私がポスドクとして2年弱ほど滞在していたノルウェーのオスロ大学での経験です.所属していた理学部化学科の研究室は,ノルウェー人以外に,中国,ロシア,セルビア,スペイン,インドと様々なバックグラウンドを持つスタッフと学生で構成されていて,女性も多く在籍していました.ノルウェー中央統計局のデータを見ると,2020年のノルウェーにおける大学生全体の男女比は4:6と女性が過半数,自然科学および工学系の学部では1/3が女性です.私が学生だった頃の東京大学材料工学科は,女子が一学年に数名,いない年もあったので,全く違う状況に驚きました.オスロ大学には日本の大学には無いシステムも多くあったのですが,特に印象に残ったのはキャンパス内に「学生用の保育園」があったことです.オスロ大学には社会人になってから入学する学生も多く,そうした学生の学びやすさを支援するための仕組みが用意されていました.我々が「できない」と思い込んでいるだけで,日本の高等教育の環境にはまだ多くの伸び代があるかもしれません. (ファインセラミックスセンター 桑原 彰秀) |
| セラミックス誌 2022年1月号掲載 (No.21) |
今回,「ダイバーシティと男女共同参画社会」について執筆する機会を頂きました.そこで,何を述べようかと考えたとき,特に議論したい話題がなく困ってしまいました.その理由は以下に述べるとおりであり,私が恵まれたキャリアを送ってきたことを認識した次第です. (神奈川大学 本橋 輝樹) |
| セラミックス誌 2021年10月号掲載 (No.20) |
先日,海外大学の先生による国際セミナーにオンラインで参加しました.大学紹介のスライドで学内の男女比を示していましたが,学生の50%,教職員の40%が女性とのことです.北海道大学の女性比率は,学生の30%,教職員の15%でした.この大きな差は今後どれくらいで解消されるのかと少し不安になります. (北海道大学 鱒渕 友治) |
| セラミックス誌 2021年7月号掲載 (No.19) |
ダイバーシティ=多様性と聞くと思い出す映像がある.あるシンポジウムで上映された陸上トラックを疾走する高桑早生さんの姿だ.彼女は中学生の時に病で左膝下を失ったが,日本を代表するパラアスリートになった.多様性のある社会とは,ジェンダーフリーだけを指すのではあるまい.障害者も老人も子供達も子育て世代もいて,それぞれが当たり前に活躍できる社会のことだ. (ファインセラミックスセンター 木村 禎一) |
| セラミックス誌 2021年5月号掲載 (No.18) |
「男子德あるは便ち是れ才,女子才無きは便ち是徳なり.」 (名古屋工業大学 辛 韵子) |
| セラミックス誌 2021年1月号掲載 (No.17) |
私が大学に入学したのは,女性研究者の割合を増大する働きが活発になってきた時期でした.学部は比較的女性比率の高い有機化学系でしたが,その当時は女性比率が2割程度でした.その後,女性比率が増大してはいるものの,依然3割程度です.この原因は,個人的には研究職は男性がなるものという潜在意識のためかなと考えております.私自身の話になり恐縮ですが,最近,妻との会話の中で子供を動物園に連れていくのを「家族サービス」と発言したところ,サービスとは何と偉そうな言葉だ,サービスではなくそれは当たり前のことだと言われました.今まで,全く違和感のない言葉でしたが,特別意識していなくても,男性が仕事,女性が家事・育児との古い潜在意識がこの発言に繋がっているのかなと気づかされました.単なる一例ですが,言われるまで気づかない潜在意識とは難儀なものであると実感しました.今後,ダイバーシティ等の仕事に係ることがあれば,このような潜在意識を変え,ダイバーシティ推進の力になれるよう頑張りたいと思います. (産業技術総合研究所 中島 佑樹) |
| セラミックス誌 2020年10月号掲載 (No.16) |
5歳息子の母である.ポスドク時分,育児と研究の両立に悩み,周囲の研究者に聞いて回った.いわゆるロールモデルを探していたわけだが,話を聞けば聞くほど,ものすごく優秀じゃないとできないじゃないか・・・と落ち込み,研究者への道を諦めていた時期があった.そんな中,留学の機会に恵まれた.息子を置いて単身留学した私を非難する声は意外にも無く,拍子抜けした私がさらに圧倒されたのは,育児の有無に限らずプライベートをおろそかにしない研究者の姿であった.「Are you happy?」と研究者仲間によく聞かれ,留学当初は即答できなかった私も,「誰かとの比較じゃない.自分が幸せかどうかだ」と気付いた.アカデミックポジションに身を置くことに何度も二の足を踏んだ私は,2018年にようやく,「若手か?」という年齢に達してからの助教となったが,人にも環境にも恵まれて幸せだ. (岐阜大学 高井 千加) |
| セラミックス誌 2020年7月号掲載 (No.15) |
筆者は2016年度から3年間,本務先のハラスメント防止対策室室長を務めた.防止対策室は2009年に設置され7年経過しているとはいえ,体制も整わないなか,途切れることなく持ち込まれる新しい事案の対応に追われた.当時はマタハラ,アルハラ,オワハラなどハラスメントをつけた新しい言葉が次々生まれていた時期でもあった.防止対策室が相談や防止に対する啓発活動を行う組織であるのに対し,起こってしまった事案に対し調査,調整,調停を行うのがハラスメント防止委員会である.その委員長して,法務・コンプライアンス担当副学長であった宮本由美子先生が就任した.宮本先生は元裁判官の弁護士で,実務家として法科大学院の教育にたずさわっていた.当時岡山大学は全国に知られるようなハラスメント事案を抱えており,宮本先生無くしては大学の正常化は大きく遅れていたであろう.そんな宮本先生はハラスメント防止に道筋をつけるさなか病を得,在職中にお亡くなりになるという悲劇に見舞われた.企業や大学のみならず省庁や政治家をも含んでまだまで続くハラスメントに,泉下の宮本先生はなんといわれるであろうか. (岡山大学 岸本 昭) |
| セラミックス誌 2020年4月号掲載 (No.14) |
理工系分野にいる女性研究者はその研究人生を多くの男性に囲まれて過ごしてきたと思うが,私自身はその反対で女性の多い環境で過ごしてきた.学生時代は同期の半分は女子,ポスドクをしていたポルトガル・ポルト大学では9割が女性研究者,客員として滞在していたイタリア・トリノ大学の研究室もボス以外は全員女性,そして研究室を立ち上げた際も当初は女性だけという状況であった.海外では出産ぎりぎりまで働き(出産予定を聞くと明日とか),出産後半年も経たず復帰し,子供を連れて研究室へ来る女性研究者ともたくさん接してきた.研究室を運営するようになってからは,非正規雇用の支援職員の方の出産・育児を,未経験者である私がどのようにサポートできるのか考えなくてはいけない状況である.それぞれの環境や立場でサポートできる内容やして欲しい内容が異なるため,その場その場で会話をしていくことは大変重要である.日本はまだ作られた仕組みを利用する立場でいるだけの女性の方が圧倒的に多い.出産・育児を経験した女性達がもっと上司という立場になれば,よりよい形になっていくのではないかと思っている. (九州工業大学 城﨑 由紀) |
| セラミックス誌 2020年1月号掲載 (No.13) |
私の研究室は女子学生と留学生の数が多いため,まず,日本における“女子学生”の誕生について調べました.1913年,創立から間もない東北帝国大学は,独自の判断で4名の女性の受験を認め,3名の日本初「女子学生」が東北大学で誕生したのが始まりです.それからまた期間が空きましたが,1922年,2名の女性が理学部数学科に聴講生として入学され,翌年から,正規の学生として毎年女子学生が入学するようになったそうです.私が所属している研究科では,女子学生は全体の約3割を占めておりますが,私の研究室では,特に女子学生の数が多いです.一時期,日本人の学生は女子学生のみとなった期間もありました. (東北大学 殷 澍) |
| セラミックス誌 2019年10月号掲載 (No.12) |
『女性研究者』に注目が集まることが多々ありますが,性別が女性で研究をしている人のことですので,既婚,未婚,子どもの有無にかかわらず,女性の研究者は『女性研究者』です.今はまだ人数が少ないので良くも悪くも注目される機会が多いのでしょう.女性研究者を増やすためには,工学系に進学する女子学生を増やす必要があります.工学分野を目指す子ども達を増やせるよう,彼女たちの憧れの存在となるべく,カッコよく,スマートに,楽しく働きたいものです. (九州大学 稲田 幹) |
| セラミックス誌 2019年7月号掲載 (No.11) |
今回,本欄執筆のお話をいただき,「ダイバーシティ(Diversity)」と男女共同参画社会について考える機会を頂戴しました.これまでも先生方が述べられているようにSTEM(Science, Technology, Engineering and Mathematics)分野で学ぶ女子学生の少なさは日本のみならず国際的な課題となっていると聞きます.私自身は研究職を目指すことに全く反対された事ありません.しかし,オープンキャンパスでお会いする方や,周囲の女性と話していて感じるのは,理系に苦手意識を持つ母親や理系を敬遠する女性が多いということです。私はこの女性自身の意識から変えていく必要があると考えています.STEM分野の女性研究者のための環境整備と促進事業が展開され,多くの取り組みが進められております.同時に,今の女性研究者の多様なライフスタイルとロールモデル,そこから学ぶキャリアパスを社会に示し,女性のもつ価値観を変えていくことも大事と考えます.そのために,私には何ができるか,何をすべきかを考えながら,今日も頑張りたいと思います. (大阪大学 後藤 知代) |
| セラミックス誌 2019年4月号掲載 (No.10) |
皆様は,自分の所属する組織がどのようなダイバーシティ推進に取り組んでいるかを具体的にご存知でしょうか?筆者は昨年まで,いくつかの取組について漠然と知るのみでした.今年度,所内のダイバーシティ推進室へ出向となり,女性の活躍推進,外国人研究者の支援,ワーク・ライフ・バランスの実現等,多岐にわたる取組を行う中で,ようやく状況を把握できてきたように感じます. (産業技術総合研究所 中村 真紀) |
| セラミックス誌 2019年1月号掲載 (No.9) |
日本の女性研究者割合は諸外国に比べて低く,中でも理工系分野において特に低い状況です.改善のための様々な取り組みがなされていますが,現場の研究者は,そもそも理工系に進学する女子学生が少ないのだから仕方ない,と諦めに似た気持ちを抱きがちです.先日,科学史を専門とする研究者から「理工系研究職に女性が少ないのは,一部の層の関心しか集めない状況を放置してきた結果」という趣旨のご意見を頂きました.これまでは,昼夜問わず実験・研究に没頭できる体力・気力・家庭環境の三拍子揃った一部の人材が理工系研究職を選び,この分野を支えてきたのでしょう. (産業技術総合研究所 大矢根 綾子) |
| セラミックス誌 2018年10月号掲載 (No.8) |
「貴方は変わっているから,研究者に向いていると思う.」父から言われたこの言葉は,筆者の進路決定に大きな影響を与えた.ならばと研究の世界に入って早20年.周囲には,さらに変わった(誉め言葉だと思う),個性的な研究者が多くいる.特に女性研究者は,際立って個性を発揮していると感じる.そのような方と接すると,感服すると同時に,筆者にはこのようなオーラはないと落ち込んでしまう.名古屋大学男女共同参画センター長の束村博子先生は,「控えめな研究者がいてもいい.多様な研究者がいるからこそ,後に続く人が出る.」とおっしゃって下さる.この言葉にいつも励まされている. (名古屋大学 鳴瀧 彩絵) |
| セラミックス誌 2018年7月号掲載 (No.7) |
1960年代の米国では平等を求める黒人による公民権運動の嵐が吹き荒れました.このとき反対派は,人種だけでなく性別による差別をも禁止する条項を加えて反対者を増やし,公民権法案全体の否決を狙ったのですが,法案は可決,結果的に女性は大きな権利を手にしたのでした.すなわち、女性が大統領候補になる米国でさえ、女性が男性と平等の権利を獲得したのはわずか50年前,しかも,それは人種差別撤廃のおまけという棚ぼた的なものだったのです.また,多くの国際機関が立地するスイスは、平和と平等の国のような印象がありますが,実はこの国で女性参政権が完全に認められたのは,なんと1991年のことです.このように男女雇用機会平等の歴史は実はまだ浅いのです.それでも,日本の雇用環境は,女性が結婚とともに離職する寿退社が当然だった30年前とは様変わりしています.私の学生時代に女性の教授を見かけた記憶はほとんどありませんが,今では研究教育の場で多くの女性が活躍しています.道は半ばです.あせることなく,多様性をパワーとする社会に向けて地道に努力していくことこそ重要であると思います. (慶應義塾大学 今井 宏明) |
| セラミックス誌 2018年4月号掲載 (No.6) |
仕事は人が動かすもの,どんな仕事にも個性が反映されています.「こんなスゴイ研究をどんな人がしたのだろう?」という素朴な疑問から,その人に会ってはじめて性別や国籍が分かり,バックグランドや人柄を知り,その研究に対する理解が一層深まったという経験をお持ちの方は多いと思います.個性は生まれつき備わっている先天的要素と環境によって育つ後天的要素からなると聞きます.成人の個性は後天的要素が大部分を占めているように思いますが,ある年齢を超えると固定化してしまうようにも感じます.仕事を進める上で,多様な個性を一様に尊重するのは至難の業と言っても過言ではないでしょう. (産業技術総合研究所 加藤 一実) |
| セラミックス誌 2018年1月号掲載 (No.5) |
本欄の第5回目の担当としてバトンを渡されましたので「女性研究者の昇進」について述べてみます.第3回目の安盛 敦雄先生は東京理科大学材料系学科に所属する女子学生の割合を分野別に調べられています.そこで私は女性のプロの研究者について述べてみます. (日本セラミックス協会会長 平尾 一之) |
| セラミックス誌 2017年10月号掲載 (No.4) |
私の所属する村田製作所はセラミック電子部品を主力とした部品メーカーです.海外売上比率は90%以上と高く,グローバルに事業展開しています.海外にも生産拠点を持ち,主要ビジネスである通信市場だけでなく,M&Aを活用して事業展開を行っています. (株式会社村田製作所 福盛 愛) |
| セラミックス誌 2017年7月号掲載 (No.3) |
指導的な地位に占める女性の割合の目標を表す「202030」が決まってから10年以上経ち,2020年まで残り3年となりました.そこで,数字を少し調べてみることにしました.私の所属する材料系学科の女子学生の割合は約20%で,大学全体でも20%を少し超える数字です.その中で,化学系は30%程度,生物系や薬学系では50%ですが,機械系や電気系は10%以下です.次に協会の会員数(2017. 3現在)をみますと,学生会員の女性比率は約17%ですから,化学系と機械・電機系の中間で,私としては何となく頷ける数字ですが,個人会員(つまり就職後)になると約5%と大幅に下がります.しかし30歳以下の若手に限ると12%に上がります. (東京理科大学 安盛 敦雄) |
| セラミックス誌 2017年4月号掲載 (No.2) |
本欄の第2回目の担当としてバトンを渡されたものの,自分の生活においてあまり男女ということを意識しているわけではありません.私自身の話をすると,独身期間も比較的長く,子供も年をとってから産みましたので,自由に研究し,人と交流することに多くの時間を費やすことが出来ました.それが研究の幅を広げることにつながっているように思います.一方,現在は子供(3歳)の育児に追われる日々を過ごしており,ゆったりとした時間はほとんどありません.以前に比べると仕事をする時間は減りましたが,子育てを通じて多くのことを学び,我慢強くなったように思います.育児はほとんど保育園任せになっていますが,保育園の先生やお友達と過ごす時間を楽しんでたくましく育っている我が子を見ると仕事を続けることが親と子が成長する上で重要な役割を果たしてくれているように感じます.仕事を続けることは大変ですが,家族や友人,上司や研究者仲間の助けがあってこそ頑張れます.騒がしい子供を連れての学会参加などもしますが,温かい目で見守っていただけるとうれしいです. (物質・材料研究機構 瀬川 浩代) |
| セラミックス誌 2017年1月号掲載 (No.1) |
日本セラミックス協会は,協会をより活性化するために,2014年に男女共同参画委員会を発足させ,新しいイベントを企画・実行してきました.今回は,皆様と「ダイバーシティ」について考える機会となりますよう,日頃思っていること,悩んでいること,仕事と家庭の両立,育児や介護,グローバル化など,約500文字で思いを書いて,次の著者にバトンリレーしていきます. (男女共同参画委員長 中野 裕美) |