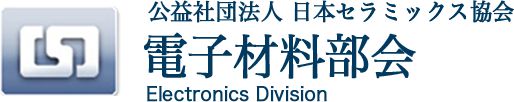エレクトロセラミックスセミナー
活動履歴
【参加募集】第43回エレクトロセラミックスセミナー
『無機基板材料の新展開』
| 主催 | 公益社団法人日本セラミックス協会 電子材料部会 |
|---|---|
| 共催 | 公益社団法人日本セラミックス協会 ガラス部会 |
| 協賛(予定) | 日本化学会、応用物理学会、電気化学会、日本材料科学会、粉体粉末冶金協会、電気学会、電子情報通信学会、電子セラミック・プロセス研究会、日本MRS、日本ゾル-ゲル学会 |
| 日時 | 2025年11月28日(金)12:30-17:30 |
| 会場 | アーバンネット神田カンファレンス |
| 参加費 | 会員:8,000円(協賛団体会員含む)、 非会員:12,000円、 学生会員:1,000円、 学生非会員2,000円 |
| 問合先 | 日本セラミックス協会 電子材料部会 〒520-2393 滋賀県野洲市大篠原2288 株式会社 村田製作所 無機材料開発部開発3課 川田 慎一郎 TEL:070-2299-0719 E-mail:s_kawada@murata.com |
セミナーのねらい
近年、半導体の微細化、高性能化、低消費電力化のトレンドに応えるため、ガラスコア、光電融合技術など無機基板材料に新たな技術が要求されてきています。
本セミナーでは、冒頭で無機基板材料に新たな技術が求められるようになってきた背景や今後必要とされる技術への期待についてFICT株式会社の雨宮社長にご講演いただいた後、当該分野でご活躍されている先生方に最新の材料やプロセス技術についてご講演いただきます。本セミナーを通し、参加者が無機基板の新たな潮流とそれに応える最新技術への理解を深め、今後の研究活動へのきっかけになることを狙いとしています。
プログラム(敬称略)
| 12:30~13:15 |
|---|
| 基調講演:次世代半導体パッケージングを支える多層ガラス基板技術の展望 FICT株式会社 代表取締役社長 雨宮 隆久 |
| 13:15~14:00 |
| 配置エントロピーを利用したガラスの熱膨張係数の新しい組成設計 国立大学法人東北大学 大学院工学研究科応用物理学専攻 光機能材料物理学分野 教授 小野 円佳 |
| 14:00~14:45 |
| ガラスのデータ駆動型超短パルスレーザー加工技術開発 国立研究開発法人産業技術総合研究所 製造基盤技術研究部門 副研究部門長 奈良崎 愛子 |
| 14:45~15:00 |
| 休憩 |
| 15:00~15:45 |
| 次世代パッケージ基板向けガラス材料の技術/事業開発動向 日本板硝子株式会社 クリエイティブテクノロジー事業部門 事業開発統括部 デジタルソリューションプロジェクト部 部長 壹岐 耕一郎 |
| 15:45~16:30 |
| シミュレーションによるガラス材料の探索 AGC株式会社 先端基盤研究所 RX推進室 室長 浦田 新吾 |
| 16:30~17:15 |
| ガラスセラミックスとフェライト共焼成技術を用いたEMIフィルターへの応用 株式会社 村田製作所 技術・事業開発本部 マテリアル技術センター 無機材料開発部 開発5課 シニアマネージャー 足立 大樹 |
講演概要
基調講演:次世代半導体パッケージングを支える多層ガラス基板技術の展望
FICT株式会社 代表取締役社長 雨宮 隆久
生成AIの急速な普及に伴い、データセンターの電力需要が世界的に増加しており、特に大規模言語モデルの学習・推論に伴う計算負荷が、電力供給に深刻な影響を及ぼしています。こうした課題に対し、電力効率の改善策として高密度チップ集積技術が注目されていますが、従来の有機基板は機械的・電気的な限界に直面しており、優れた物理特性を持つガラス基板が次世代パッケージング技術の有力候補とされています。
しかし、Through-Glass Via(TGV)製造に伴う加工の難しさや破損リスクなど、実用化に向けた技術的課題も依然として存在します。
本講演では、現時点での技術的課題を整理・共有するとともに、パッケージングおよび基板技術の進化に与える潜在的な影響について紹介します。
さらに、革新的なソリューションとして新しい多層ガラス基板を提案し、複数のガラス層上に回路を形成し部品を埋め込むことで、機能の垂直統合を実現し、高付加価値なチップパッケージングの新たな可能性を示します。
配置エントロピーを利用したガラスの熱膨張係数の新しい組成設計
国立大学法人東北大学 大学院工学研究科応用物理学専攻 光機能材料物理学分野
教授 小野 円佳
ガラスは、比較的簡単に表面を滑らかにでき、後処理で圧縮応力を加えて傷が広がるのを防ぐことが出来る材料である。建築材料などには、物理強化や熱強化と呼ばれる方法でこの後処理が行われる。我々は、ガラスの熱膨張の特性を活かした新しい組成を設計し、物理強化に必要なエネルギーを大幅に減らすことに成功した。
今回の熱膨張係数の制御は、ガラス転移温度におけるガラスの配置エントロピーの変化を利用して行った。同様に考えればガラス転移温度以下の熱膨張係数と、転移温度以上の熱膨張係数の比を制御することが出来るため、熱強化以外の用途に調整することも可能である。
ガラスのデータ駆動型超短パルスレーザー加工技術開発
国立研究開発法人産業技術総合研究所 製造基盤技術研究部門
副研究部門長 奈良崎 愛子
産総研ではデータ駆動型超短パルスレーザー加工技術を開発している。本技術では、インプロセスモニタリングにより高効率にデータ取得し、プロセスデータベース構築やAIによるマルチパラメータの最適化、そして超短パルスレーザー技術によるプロセス高速制御を行うことで、次世代レベルの高品位・高生産性なレーザー加工を目指す。今回、ガラス表面へのナノ周期構造形成をリアルタイムモニタリングしたデータをもとに、フェムト秒レーザーパルスの強度を高速にフィードバック制御した結果、ガラス表面へのナノ加工の欠損率を30分の1に低減することに成功したので紹介する。
次世代パッケージ基板向けガラス材料の技術/事業開発動向
日本板硝子株式会社 クリエイティブテクノロジー事業部門 事業開発統括部
デジタルソリューションプロジェクト部 部長 壹岐 耕一郎
本発表では、ガラスの高耐久性と樹脂並みの微細加工性を両立するナノインプリント光学素子の技術的優位性と応用展開について紹介する。ゾルゲルプロセスを活用した微細構造形成により、様々な光学機能の付与が可能となり、次世代半導体パッケージ(Co-Packaged Opticsや光電融合型パッケージ)分野など高精度・高耐久性が求められる分野での応用が期待される。また、日本板硝子では、低誘電率・低CTE特性を有するガラスフィラーや、TGV(Through Glass Via)対応のガラス基板の技術開発/事業化にも取り組んでおり、光・電気複合パッケージに向けた材料として多様なソリューションを提供可能である。
シミュレーションによるガラス材料の探索
AGC株式会社 先端基盤研究所
RX推進室 室長 浦田 新吾
ガラス素材は、建築物やモビリティの窓ガラス、テレビ、スマートフォン、カメラなどの電子機器に加え、グラスや耐熱食器といった日常雑貨に至るまで、身の回りのさまざまなシーンで利用されている。一方で、半導体などの生産工程において、消費者の目に触れることのない隠れた部材としても重要な役割を果たしている。素材の研究開発においては、これら多岐にわたるニーズに応えるため、日々ガラス組成の最適化が行われている。その中で、計算科学やデータサイエンス、さらにはコンピュータアーキテクチャの進化により、マテリアルズ・インフォマティクスやシミュレーションの重要性が益々高まっている。本講演では、素材開発におけるデジタル技術の活用例として、外部連携により構築した破壊シミュレーション技術と、近年急速に進化している生成AIを活用したガラス組成探索の取り組みについて紹介する。
ガラスセラミックスとフェライト共焼成技術を用いたEMIフィルターへの応用
株式会社村田製作所 技術・事業開発本部 マテリアル技術センター 無機材料開発部
開発5課 シニアマネージャー 足立 大樹
近年の通信技術の発展に伴い、高周波帯域デバイスの需要が増加している。本研究は、低温同時焼成セラミックス(LTCC)材料の一種であるガラスセラミックスとフェライトを組み合わせた共焼結技術を用い、高周波に適したEMI(電磁干渉)フィルタの開発を目的とした。小型化が進む電子機器において電磁干渉対策は重要であり、磁気特性に優れたフェライトと低誘電率のガラスセラミックスの統合により、高周波性能の向上を実現した。共焼結プロセスの最適化により、次世代電子機器向けの新たなソリューションを提供し、今後のEMIフィルタ開発に要求される知見を報告する。